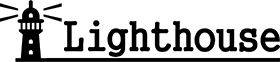【ダヴィンチニュース】障害者を支援するとき、支援者は「健常者の思い込み」に彼らを引き込んでいないだろうか?
2020年2月22日
『ありのままがあるところ』(福森伸/晶文社)は、知的障害のある人々が過ごす福祉施設を舞台とした本だ。その名を「しょうぶ学園」といい、世界から注目を集めている。著者の福森伸さんは、しょうぶ学園の統括施設長を務めてきた。
本書は、福祉や支援に関わっていない人にとっても、他者とより良く関わる上で助けになる本だ。ぜひ手にとってみてほしい。
他者を支援することはむずかしい。相手のためと考え、良かれと思って「がんばれ」とつい背中を押してしまう。福森さんは、自らが理想としていた「社会適応」のための支援を、ふと疑問に思った。
“「がんばればきっといいことがあるよ」というときの「いいこと」とは、誰にとってなのか?”
ある人が腕時計を買った。福森さんが時間を尋ねると、腕時計を見せてくれる。そこで福森さんは時間を知ることができるが、「もしかして時計を読めないのではないか?」と思い、繰り返し時間を尋ねていった。しかし彼は「わからない」と返答するのみだった。
彼にとって腕時計は、人に見せるためのものであり、時間を読むためのものではなかったのだ。そこで支援者は彼に対して、時計の読み方を教えたくなる。
しかしそれは、彼の求めるところではない可能性が高い。彼は、時計を身につけて福森さんたちに見せることで、目的を達成しているからだ。「時計は自分で時間を読むためのものだ」という考えは、支援者の側の固定観念なのかもしれない。
木彫りの器を作るとき、大きな器になる予定だった木の塊が木くずになるまで彫り続けた人がいた。「木の器にしたい」と考えているのは支援者であり、一方の彼は「ノミを木槌で叩いて彫ること」そのものに夢中になっていた。行為自体を目的とした純粋な行動だったのだ。それを止めてまで支援者、ひいては「社会」が求める姿に矯正していくことは、果たして「いいこと」なのだろうか。“こちら側には見えていない世界が向こうには広がっているのに、それが見えていない”と福森さんは考えた。
“これは繰り返し言っておきたいのだが、支援や教育という言葉で私たちが利用者に能力の向上を促そうとして接する時、勝手に彼らのテリトリーに侵入していることになっている場合が多い”
やわらかで深みのある書き口が、読者に対して、他者との関わりを深く考えさせてくれる。“本人のしきたりを理解しに行くためにテリトリーに入る”との考え方は、きっとさまざまな人々との関わりにおいて大切になるだろう。
文=えんどーこーた
記事元はhttps://ddnavi.com/review/596279/a/